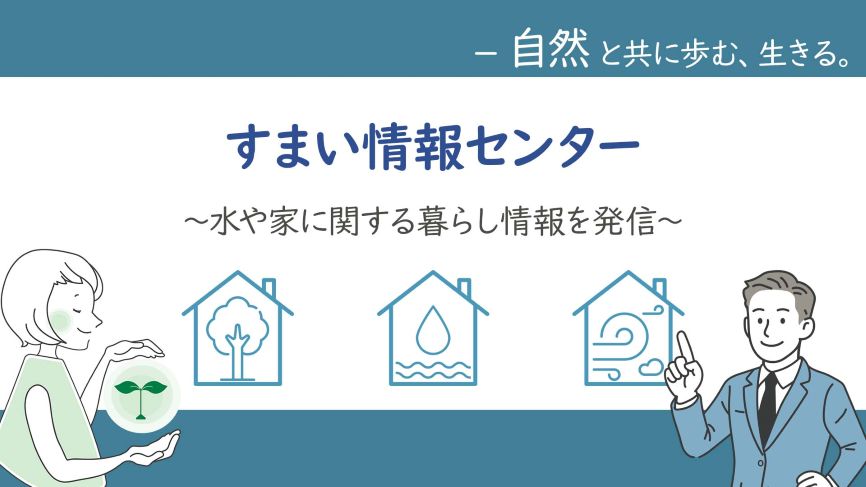
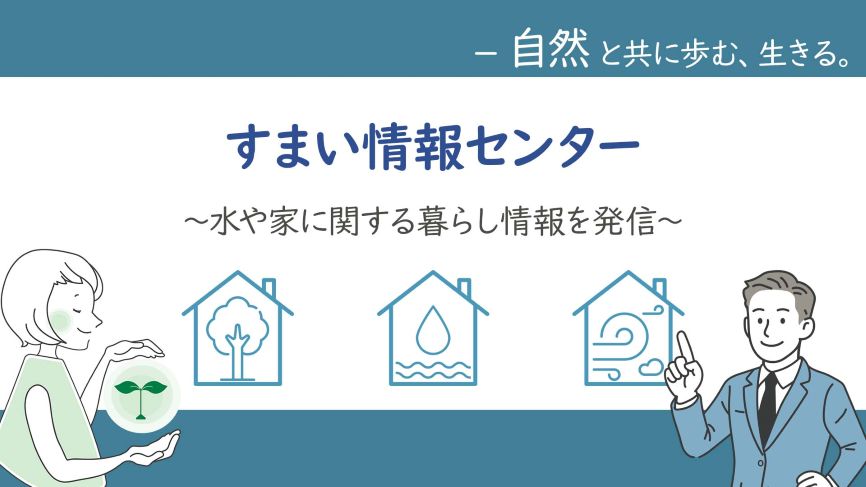
水の自給自足

水の自給自足とは、公共の水道に頼らずに水を確保し、自らの手で水の循環を築くことを指します。
井戸を掘って地下水を汲み上げる方法や、専用のプールや貯水タンクに雨水を蓄えて浄水装置で濾過する方法が一般的です。
また、水の供給だけを自給して排水は公共水道を利用するケースも見られます。
自宅に公共水道が通っている場合、自分で用意した浄水装置で水を自給自足するよりも水道水を使った方が低コストになるケースが多いです。
国内においては水道が通っていない理由や、地下水を利用した井戸水と組み合わせる方法で自給自足している人が多く見られます。
行政による取り組み
愛媛県西予市の山岳部にある一部の住宅で、水の再生循環装置を用いた自給自足の実証実験が国内で初めて行われました。
山岳地帯の過疎地域では水道設備が十分に整っていないケースもあります。
過疎化は今後も進む見込みで水道設備が老朽化していく問題もあるため、国や自治体が水の自給自足を推進する取り組みがこれから増えていくかもしれません。
浄化槽の設置

水道が通っていない場所で水を自給自足する場合は下水の適切な処理が必要です。
トイレには循環式自己処理型バイオトイレなどがありますが、台所や洗濯機の排水に含まれる洗剤などの水は適切に処理しないと環境汚染の原因となります。
下水道へ排水できない環境では、浄化槽を設置して汚水を処理した状態で再利用したり、河川などへ排水したりすることが必要です。
水道管が通っていない地域で生活したい場合は国や自治体、管轄の水道局から必要な機材の購入費用の一部が補助されるケースもあります。
ただし、キャンプ場のような営利目的の施設を作る場合は、基本的に自費で必要な設備を揃えないといけません。
機材が進化している


増加する自然災害や過疎化による水道設備の維持問題などを背景に、水を自給自足するための設備が需要を高めています。
循環装置や浄化槽など新型の装置が次々と開発・発売されており、一昔前に比べて水の自給自足をするハードルが下がりました。
従来よりも安価に導入できる製品やランニングコストを抑えられるものが登場していますが、水を完全に自給自足するのは依然として難しいことが多いです。
上水や汚水処理には定期的にカートリッジを交換するなどのコストがかかります。水道料金を支払いたくないために自給自足を目指すのは必ずしも合理的とは言えません。
多くの人が水道が通っていないことを理由に自給自足を考えていますが、近年では防災対策として水の自給自足を目的とした装置を導入する事例が増加しています。
水の枯渇リスク

水を自給自足する上で大きな課題になるのが、雨不足や過剰な利用によって水資源が枯渇するリスクです。
大きなタンクや貯水槽を備えていても、雨が少ない時期や季節には必要な水量を確保できない場合があります。
水の自給自足を実践している人の多くは、入浴時の水を節約するなどの工夫を行っています。
トイレは水洗式以外の方法に切り替える必要性が高く、水道が通っている家庭に比べて快適性が損なわれるケースも少なくありません。
飲み水の確保が難しくなると生命の危機に直結するため、水の残量や補給の見通しを確認しながら計画的に水を使用する必要があります。
沢水・湧き水の活用

近隣に沢水や湧き水があるなど周辺環境によっては、ポンプなどで自然の水を自宅に引き込み、生活用水として利用できるケースがあります。
天然水は水道水よりも美味しいと評判ですが、滅菌処理が施されていないため長時間の保存は難しいです。
さまざまな理由で細菌が混入する可能性があるため、自然由来の水源から自給自足を行う際は衛生管理を徹底する必要があります。
ホースを使って天然の水を引き込む場合は、定期的なメンテナンスも欠かせません。
大雨などによって濁った水しか調達できなくなることもあるため、沢水や湧き水に依存した生活を考える際は十分に注意しましょう。
水の自給自足は素人が安易に始めると予期せぬトラブルを招くことが多いため、専門家に相談しながら必要な機材を整えて計画的に進める必要があります。