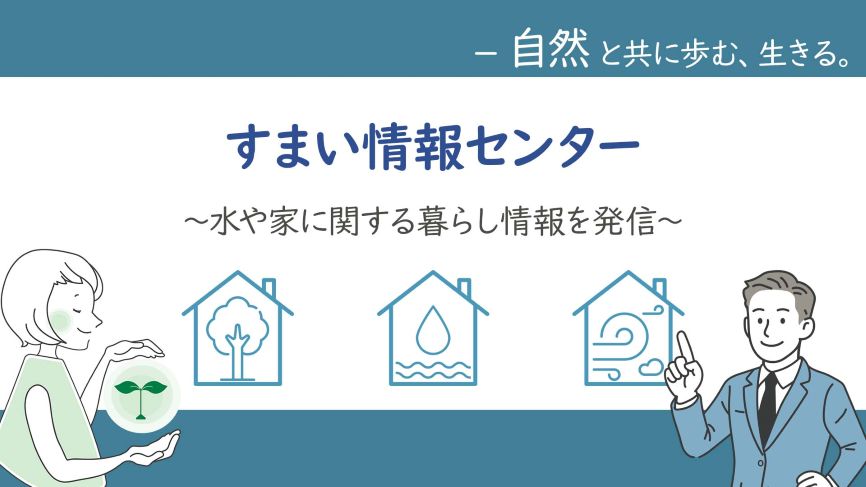
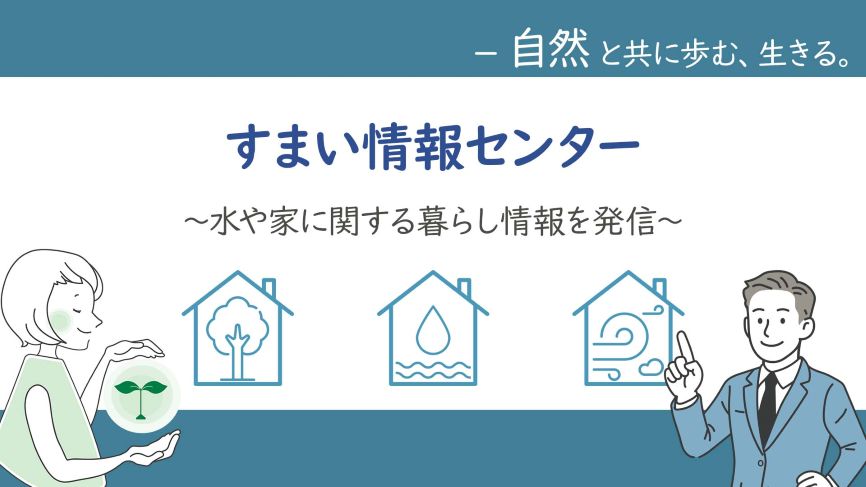
一般家庭の水道
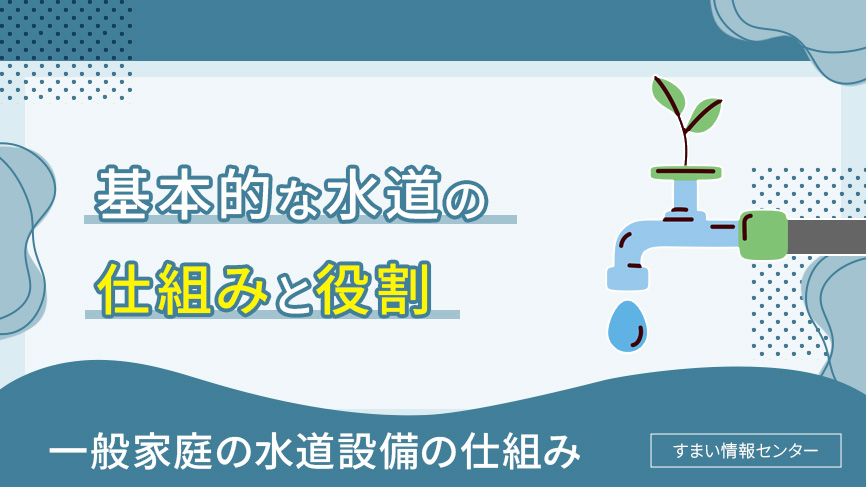
私たちの生活に欠かせない水道設備は、快適で衛生的な暮らしを支える重要なインフラです。
ここでは、家庭内の水道設備の基本的な仕組みと役割、料金などについてわかりやすくご説明します。
水源からの流れ
私たちの家庭に水を供給するためには、まず水源から水を引き込み、最終的に家庭内へ届ける仕組みが必要です。
水源は河川・湖・ダム・地下水などさまざまで、日本は一部の離島を除いてほぼ全ての家庭に品質基準をクリアした水道水を届けられるインフラが整っています。
自然由来の水源が豊かではない地域はダムを建設するなどして、水不足のリスクが少ない環境を作ってきました。
水源からは水道管を伝って管轄の水道施設や家庭に水が届けられる仕組みです。
京都市が使う水の99%は滋賀県の琵琶湖を水源にしている話が有名で、水道管や水路を使って他県まで水を届けるインフラが整っているケースもあります。
浄水処理
 水源から取水された水は取水施設や浄水場に送られます。ここで泥や不純物、微生物などを除去するための浄水処理が行われ、安全な飲料水として供給できる状態に整えられます。
水源から取水された水は取水施設や浄水場に送られます。ここで泥や不純物、微生物などを除去するための浄水処理が行われ、安全な飲料水として供給できる状態に整えられます。
一定の品質基準をクリアした安全な水が上水として各家庭に届けられていますが、一般的にダムを水源にしている地域より地下水を水源にしている地域の方が水道水が美味しいです。
水質に若干の差があるほか、水道代も地域によって変わります。
水道代の違い
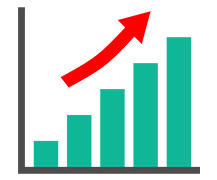 浄水場での処理や配水管網の整備・維持管理には費用がかかり、地域の地形やインフラの整備状況によってコストが異なって水道代にも差が出ます。
浄水場での処理や配水管網の整備・維持管理には費用がかかり、地域の地形やインフラの整備状況によってコストが異なって水道代にも差が出ます。
管の長さや老朽化の程度も地域差の一因で、水道代が安い地域と高い地域では約8倍も差があるなど地域格差が非常に大きいです。
電気やガスは契約する会社を変えて料金を見直すことが可能ですが、水道は原則として地域の決まった水道局と契約しないといけません。
住む地域を変えない限り、水道代の単価を低くすることが難しいです。
地域・管轄の水道局ごとで設定された水道料金を受け入れ、それに合わせた予算を組んで生活する必要があります。
下水の流れ

使用済みの水は排水管を通じて下水道へと流れ、最終的には下水処理場で浄化されて海や川などの環境に戻されます。
下水管へ排水されていく水をそのまま自然に流すだけでは環境や健康にさまざまな問題が生じるため、下水処理の役割は非常に重要です。
排水には油脂・汚れ・微生物・化学物質など多くの汚染物質が含まれて、下水処理施設ではそれらの汚染物質を除去して消毒をしています。
適切に処理しないと環境汚染だけではなく、感染症の原因になって悪臭などを発生させるなど多くの問題が発生します。
適切な下水処理を行うことで処理水を再利用したり地下水や河川の水質を維持したりすることが可能になり、限られた水資源を効率的に活用できて持続可能な社会の実現に寄与するのです。
環境問題という面では水の無駄遣いを減らすことよりも、下水を適切に処理することの方が大切です。
下水処理施設があるとはいえ、廃油を水道管に流さないなど各家庭が適切な方法で排水する必要があります。
水道管の耐用年数
 水道管の多くは地下に張り巡らされていて、ほぼ全ての家庭に水道を利用できる分だけの長さを誇ります。
水道管の多くは地下に張り巡らされていて、ほぼ全ての家庭に水道を利用できる分だけの長さを誇ります。
水道管の耐用年数は40年とされていますが、交換などのメンテナンスが追いついておらず、令和2年度末時点で全体の約2割が耐用年数超えの老朽化した水道管を使い続けているのが現状です。
道路陥没事故や能登地震で水道インフラに壊滅的な被害が出るなど、既に水道管が老朽化している影響が出てきています。
今後も老朽化した水道管の比率は高まる見込みで、人口密度が低い地方では水道代が大幅に値上げされるかもしれません。
避けては通れない問題ですので、水道代の値上げに備えて日頃から上下水道の使用量を節約する取り組みを始めておくとよいでしょう。