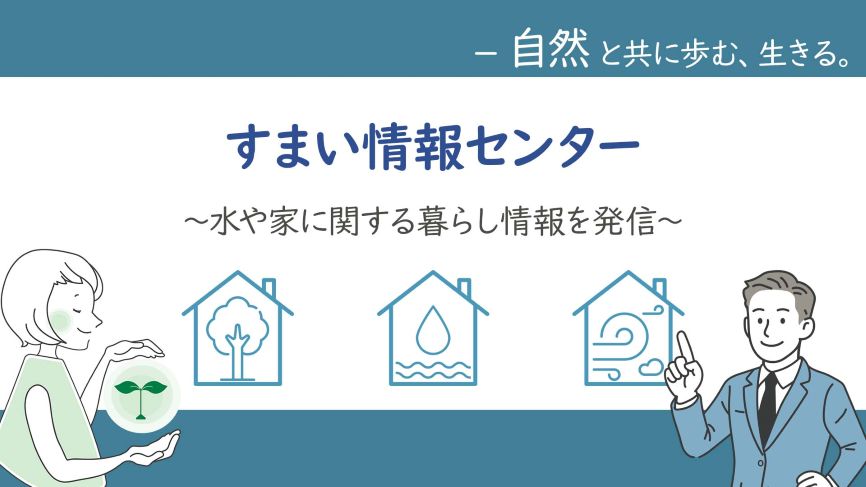
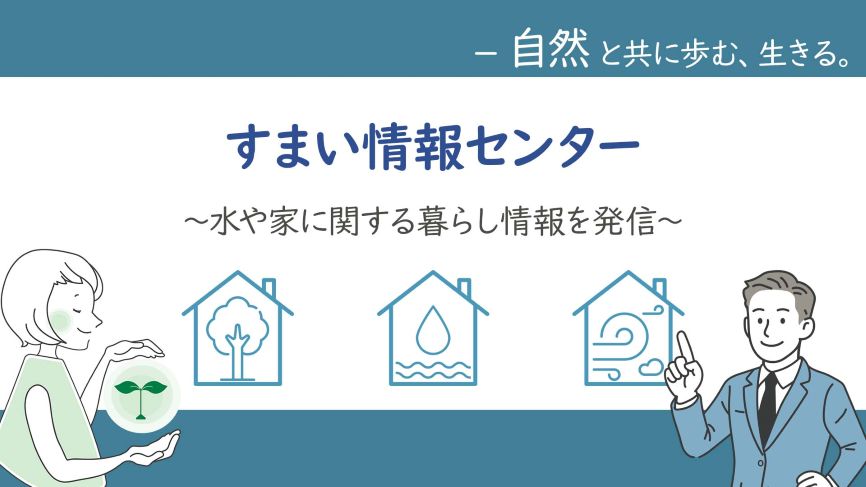
降水量とダムの仕組み
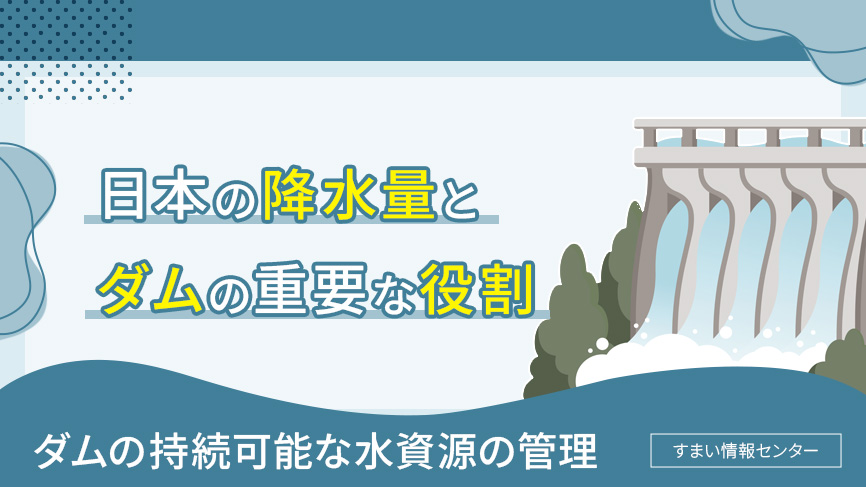
日本は世界の中でもトップクラスに水道インフラが整備されています。
全国的に降水量が多く、各地に建設されたダムによって水不足のリスクが少ない環境が整っています。
日本は降水量が多い
 日本の年間降水量は平均して1,500mm~2,000mmで、世界的に見ても降水量が多い地域に属しています。
日本の年間降水量は平均して1,500mm~2,000mmで、世界的に見ても降水量が多い地域に属しています。
梅雨や台風の影響で短期間に降水量が増加しやすいのが特徴で、地域によっては年間2,500mmを超える場所もあります。
日本よりも降水量が多い地域には、南アメリカのアマゾン流域や東南アジアの一部地域などがあり、年間降水量の目安は3,000mm前後です。熱帯雨林気候やモンスーン気候の影響を受ける地域は、降水量が多くなりやすいです。
日本は温帯気候に属し、四季の変化や台風、梅雨前線などの気象条件によって年間降水量は比較的高い水準で安定していて、農業や水資源の面で重要な役割を果たしています。
降水量が少ない地域には中東や北アフリカの一部、中央アジアの乾燥地域などがあり、砂漠地帯では年間降水量が200mm未満となるケースもあります。
極端に降水量が少ない地域は、砂漠気候やステップ気候に属していることが多いです。
ダムの仕組みと役割

 ダムは川や湖の水を貯めるための巨大な構造物です。基本的な仕組みは土やコンクリートで作られた壁で水をせき止め、ダム湖とも呼ばれる貯水池を形成します。
ダムは川や湖の水を貯めるための巨大な構造物です。基本的な仕組みは土やコンクリートで作られた壁で水をせき止め、ダム湖とも呼ばれる貯水池を形成します。
ダムによってせき止められた貯水池では大量の水を蓄えることができ、ゲートや放流口によって意図的に水位を調整することが可能です。
なお、ダムには人工的に作られたものだけではなく天然で作られたものもあり、川をせき止めて形成したものは天然ダムに分類されます。
ダムの役割は主に洪水の防止・水資源の確保・水力発電による3種類があり、適切な水の流れを管理することで河川の生態系を守ることにも大きく貢献しています。
自然本来の川だけだった場合は大雨や台風で河川が氾濫して洪水被害をもたらすリスクがあるため、水資源の確保ではなく洪水防止を主な目的にしつつ、河川の水位調整と水力発電をするために建設されたダムも多いです。
生活用水の水源をダムに依存している地域もあり、雨が少なくてダムの水位が低くなると水不足で水道の使用制限をされるケースがあります。
ダムの水位
ダムによって若干の違いはありますが、一般的に運用時の水位は50~80%程度が望ましいとされています。
貯水率が20%を下回ると水不足や水道の供給制限が必要となる状況です。
貯水率が高すぎると大雨や台風に対応できなくなるため、水位が高い時には放水で調整を行います。
多くのダムは山岳地帯に建設されており、大雨が降ると周辺の山から流れてくる水によって一気に水位が上昇します。
日本で最も貯水量が多いダムは岐阜県の徳山ダムです。
東京ドーム1,400個分に相当する6,600万立方メートルの貯水量を誇り、これは約330万世帯分の水道水1年分に相当します。
日本のダム
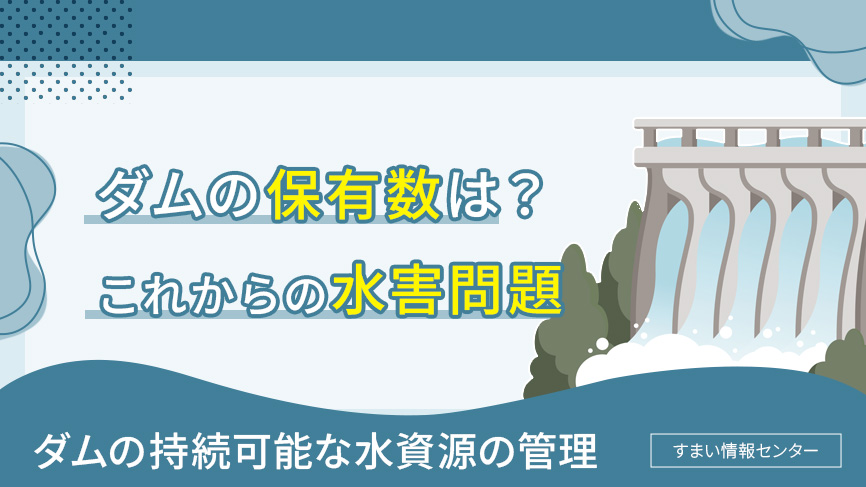
高さ15メートル以上をダムと定義した場合、日本全国には約3,091基のダムがあります。建設中のダムも複数あり、ダムの数は今後も増加する見込みです。
日本は狭い国土にも関わらずダムの保有数は世界第3位です。これは地形がダム建設に適していることや、水資源を活用した農業が盛んなことが関係しています。
ちなみに、世界でもっともダム保有数が多いのは中国で、2番目はアメリカです。
日本はダムが多いため、降水量が多いにも関わらず洪水などの被害は比較的少ないです。しかし、昨今は地球温暖化の影響で記録的な豪雨による被害が全国各地で頻繁に発生しています。
ダムにはキャパシティがあり、降水量が非常に多い場合は既存のダムだけでは対応しきれず、大規模な洪水被害が発生することが増えました。
今後は新たなダムの建設も計画されていますが、地球温暖化による異常気象の影響で水害や水不足の問題がより深刻化していくかもしれません。